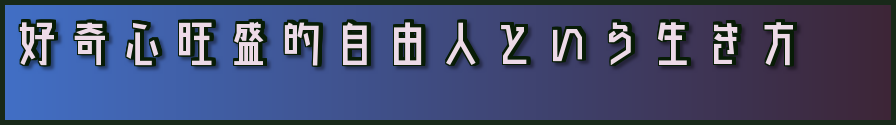どうも、koukiです。
今回は、サイト作成文章の書き方や構成について書いていきます。
書き方については参考になるサイトを見て、そこで無料で学ぶことができます。
文章を書くひとつの参考として読んでください。
どちらかといえば、私自身に向けた記事となります。
 サイト運営でも同じです。
第一に何度も続けることが必須だといえます。
数字を気にするもの悪いことではありませんが、まずは新しいことを始めて、それを継続して成長していくことを楽しむことが大切です。
やればやるほどそれなりに書けるようになりますし、アクセスも自然に増えていきます。
アクセスが増え始めると、それでまた面白くなる。
Twitterやインスタグラムなどでの集客はとても大切なことですが、それを先にではなく、平行もしくはその後でもよいと思います。
小手先のテクニックよりも、まずは文章を書くことに慣れるという『土台』が大切。
サイト運営でも同じです。
第一に何度も続けることが必須だといえます。
数字を気にするもの悪いことではありませんが、まずは新しいことを始めて、それを継続して成長していくことを楽しむことが大切です。
やればやるほどそれなりに書けるようになりますし、アクセスも自然に増えていきます。
アクセスが増え始めると、それでまた面白くなる。
Twitterやインスタグラムなどでの集客はとても大切なことですが、それを先にではなく、平行もしくはその後でもよいと思います。
小手先のテクニックよりも、まずは文章を書くことに慣れるという『土台』が大切。
![]() 小学生に起承転結を求める当時の文部省はどうかしてるぜ!というか書いていくうちにわかったことですが、ブログどころか作文にすら起承転結は全く使えません。
物語を書くならば、映画を作るならばまだしも、行動や経験作文には適応するものではありません。
ましてや、ブログやアフィリエイトにも全く使えないということです。
作文やブログ記事については、報告書のような書き方が適しています。
結論と概要が先に来るという書き方。
簡単にその書き方の一例として説明してみます。
小学生に起承転結を求める当時の文部省はどうかしてるぜ!というか書いていくうちにわかったことですが、ブログどころか作文にすら起承転結は全く使えません。
物語を書くならば、映画を作るならばまだしも、行動や経験作文には適応するものではありません。
ましてや、ブログやアフィリエイトにも全く使えないということです。
作文やブログ記事については、報告書のような書き方が適しています。
結論と概要が先に来るという書き方。
簡単にその書き方の一例として説明してみます。
![]() 剣道などの武道では『守破離』という言葉があります。
これは書籍として出版されていますが、実はそのままインターネット上で読むことができます。
2,000円する書籍ですが、それを無料で読むことができるという時代の異常さ。
非常に参考になりますが、無料でウエブ上で読めますから買う必要はありません。
本のほぼ全てが読むことができますが、本を買えば更に・・・という部分を保つことで本を売る方法です。
実際に書籍であること、それが通常の価格で販売していること、それを無料でウエブ上で読むことができること、それがこの本の販売戦略であることを理解してもらえると思います。
石ころだって先生です。
全ての事象や有機物、無機物から学ぶことはあります。
剣道などの武道では『守破離』という言葉があります。
これは書籍として出版されていますが、実はそのままインターネット上で読むことができます。
2,000円する書籍ですが、それを無料で読むことができるという時代の異常さ。
非常に参考になりますが、無料でウエブ上で読めますから買う必要はありません。
本のほぼ全てが読むことができますが、本を買えば更に・・・という部分を保つことで本を売る方法です。
実際に書籍であること、それが通常の価格で販売していること、それを無料でウエブ上で読むことができること、それがこの本の販売戦略であることを理解してもらえると思います。
石ころだって先生です。
全ての事象や有機物、無機物から学ぶことはあります。
もくじ
文章作成の学び方
何か文章を際、多くの人は小学校で習った方法で文章を書いています。 学校で習ったひらがな、カタカナ、漢字、言い回しを使って文章を作成いるはずです。 なぜなら、文章の書き方は小学校で学ぶ以外にほとんど学ぶ機会がないからです。 仮に文章を学ぶ機会があるとすれば、それは大学の論文であったり、仕事で必要に迫られて学ぶ報告書的な文章です。 論文や報告書は、何かの本で学ぶことよりも、誰か他の人の文章を読んでいくような伝承的で独学的な学び方になります。 このブログでもそうですが、まずは自分でひたすら文章を書いていきます。 ブログは自由です。 日記を書いたり、趣味を書いたり、主張したいことを書いたり。 好きなことを好きなだけ書いていくことに縛りはありません。 そのうちに、もっと面白く書けないか、多くの人に読んでもらえないだろうか、と考えるようになります。 そのために文章能力やサイトの構成について考えるようになります。 そして他人のブログを読んで学んでいます。 学ぶの原点である『真似ぶ』(学ぶの語源は真似をする) による他人のブログ文章を読んで技術を盗む方法が一般的です。 技術を習得するためには多少のお金を払うことは投資ですので、有料教材を買うこと、それも正解です。 文章を書く方法については様々な場所で情報を入手できます。 今ならばTwitterやYoutubeでも無料でブログを書く知識を学べたり、考え方などのエッセンスも示してくれています。 お金をかけない分、本気になりきれないかもしれませんが、無料でも有益な情報には間違いありませんので、学ぶ気のある人にはとても良い時代です。 結論として必要な情報を本を買ったり、講義にいかなくても、真剣に求めれば無料で必要な情報が得られます。 今回は- ブログ文章の特徴
- 文章の構成について
- 書き方について書いてある本やヒントはどこに転がっている
- 有料と無料の違い
- 結論、無料で充分に勉強や習得できる
ウエブログ(ブログ)を学びながら継続する楽しさ
私が文章の書き方を習ったのは小学校です。 そのうえで、学校での論文や仕事で作成する報告書などの書き方は必要に迫られて、本や他人のものを読んで必要部分を独学で学んだものです。 つい最近まで、文章の書き方といった本や教えをことさらに求めたことはありませんでした。 このブログでは、完全に私の成長軌跡が綴られています。 この稚拙なサイトを隅から隅まで読んでいただくことはないでしょう。 しかし、当初の文章を読んでいただければわかりますが、現在に至るまでただひたすらに稚拙な文章で綴られています。 それでも徐々に成長していることは実感としてあります。 それは私がブログを運営しながら文章を作成する能力を求めて、実践して、学んでいるためです。 現在のところ、サイトも記事の書き方も完成することはあり得ません。 逆に言えば、のびしろがあるというよりも、成長しか感じないという段階です。 やればやるほど文章を書く速度は上がり、誤字脱字も減り、文章構成もそれなりにうまくなっていきます。 RPGゲームと同じです。 最初は右も左もわからないのに、慣れ始めてくると明らかな成長を感じることができて、面白くて辞められなくなる! ということです。 会社などで報告書を書かれる方は、書けば書くほど速く上手になるということはよくわかると思います。 何事も同じですが、やればやるほど熟練していきます。 初めて自転車に乗れるようになるには何度も転んで、何度も危険な目にあいながら覚えます。 自分でトイレに行けるようになった時のことを覚えていますか? 何事も初めはうまくできません。 ですが続けるうちに最後は、自分でうまくやれるようになります。 サイト運営でも同じです。
第一に何度も続けることが必須だといえます。
数字を気にするもの悪いことではありませんが、まずは新しいことを始めて、それを継続して成長していくことを楽しむことが大切です。
やればやるほどそれなりに書けるようになりますし、アクセスも自然に増えていきます。
アクセスが増え始めると、それでまた面白くなる。
Twitterやインスタグラムなどでの集客はとても大切なことですが、それを先にではなく、平行もしくはその後でもよいと思います。
小手先のテクニックよりも、まずは文章を書くことに慣れるという『土台』が大切。
サイト運営でも同じです。
第一に何度も続けることが必須だといえます。
数字を気にするもの悪いことではありませんが、まずは新しいことを始めて、それを継続して成長していくことを楽しむことが大切です。
やればやるほどそれなりに書けるようになりますし、アクセスも自然に増えていきます。
アクセスが増え始めると、それでまた面白くなる。
Twitterやインスタグラムなどでの集客はとても大切なことですが、それを先にではなく、平行もしくはその後でもよいと思います。
小手先のテクニックよりも、まずは文章を書くことに慣れるという『土台』が大切。
ウエブログ(ブログ)文章の作成について
私はこのブログを書きながら- どのような書き方が適しているのか
- どのように書いたら楽しいのか
- どのように言いまわせば読みやすいのか
- どのような画像を入れたら見やすいか
- どのような題をつければ見てもらえるのか
- もくじを作成していない。
- 表題も文章を書いてからそれにあった表題を適当に設定する。
- 記事内の項目がない。
- 項目も作成せずに1記事を書き上げる。
- 文章始まりの結論を示さずに最後に結論を持ってくる。
- 段落も適当。
- 文章の区切りも適当。
- 強調の太文字や色文字も使用しない。
- 意味のない外部リンク。
- サイト=根を張って幹を伸ばす
- 枝=記事
- 枝からの枝=詳細記事
- 葉、花=経験した有益な情報、面白い話
- 果実=経験や面白いことを裏付ける情報、販売記事
文章の構成:起承転結は文章作成に向いていない
私は小学校の頃に 「作文は起承転結という構成で書きなさい。」 と習いました。 小学生に起承転結を求める当時の文部省はどうかしてるぜ!というか書いていくうちにわかったことですが、ブログどころか作文にすら起承転結は全く使えません。
物語を書くならば、映画を作るならばまだしも、行動や経験作文には適応するものではありません。
ましてや、ブログやアフィリエイトにも全く使えないということです。
作文やブログ記事については、報告書のような書き方が適しています。
結論と概要が先に来るという書き方。
簡単にその書き方の一例として説明してみます。
小学生に起承転結を求める当時の文部省はどうかしてるぜ!というか書いていくうちにわかったことですが、ブログどころか作文にすら起承転結は全く使えません。
物語を書くならば、映画を作るならばまだしも、行動や経験作文には適応するものではありません。
ましてや、ブログやアフィリエイトにも全く使えないということです。
作文やブログ記事については、報告書のような書き方が適しています。
結論と概要が先に来るという書き方。
簡単にその書き方の一例として説明してみます。
題名
この記事の骨格であり、何について書いてある記事なのかを簡潔に表示する必要があります。 SEO対策として、キーワードを入れた28文字だとか31文字だとかと言われます。 正しいことではありますが、それに固執しすぎても分かりづらい題名になります。記事の概要と最初の結論
記事の初めに、この記事は誰に向けて何が書いてあるのかを書く必要があります。 そして、概要と結論を最初にもってくる報告書形式の書き方です。 その詳細はその後に書かれますので、どうしてその結論になったのかを読み進めたくなる内容であればよいのです。この記事の経緯
この記事作成に至る簡単な理由があれば、同じ経験をしていたりその経験を知りたい読者の共感を得られます。経験内容
これも経緯に含まれる部分ですが、リアルな体験談などを交えることで記事の信頼性や興味がふくらんでいきます。実験、実践内容
記事のメイン部分です。 何をしたのか、何が言いたいのかを具体的に書いていきます。参考事項
この記事の内容を担保する話、引用、参考資料を説明します。その結果から得られた結論(まとめ)
結論の詳細です。 証明事項から導きだされた結論を詳細に記載して総括します。 順番を決めておくと文章としてわかりすく、見やすくなります。 これは私が記事や報告書を書く際の、私が理解している書き方です。守破離という学び方
私が学んだ文章構成はひたすらに書きながら学んだもので、現時点で至っている書き方です。 文章構成の決まりを自分で作れば効率もあがりますし、理解も深まります。 文章構成については、様々な人が分かりやすい構成方法をネット上でも、本でも教えてくれます。 様々な人の文章構成を参考に、自分自身の構成を確立していけばいいと思います。 そのためにも、何度も何度もブログで様々な書き方をしながら実験を繰り返しながら確立するわけです。 剣道などの武道では『守破離』という言葉があります。
剣道などの武道では『守破離』という言葉があります。
- 当初は師匠の教えを忠実に守って、そこから外れないように練習をしまくる。
- 基本が定着したならば、基本を更によりよく有効なものにする。
- 師匠の形よりもより自分に合った形を確立する。